「蔦屋重三郎とはいったい誰だ?」
2025年のNHK大河ドラマの主人公は全く聞き覚えのない人物。俄然、興味がわいてきました。そこで、今回はこの謎めいた人物がどんな人だったのか、詳しく調べてみました。
一言でいえば、蔦屋重三郎(1750年〜1797年/寛延3年~寛政9年)は、江戸時代に活躍した凄腕の編集者。
彼のすごいところは、広告や販促の考え方を持ち込んだところです。
本の宣伝方法として、 著名人による推薦序文や巻末の刊行目録を使い、商品の認知度を高める仕掛けを作りました。
また、現在で言うところのオンラインサロンのような文化人ネットワークを作り、作家や絵師と連携。優秀な人材を見つけ出す目利きでもありました。スカウトの能力も超一流です。才能ある作家や絵師を見抜いて、出版物に起用していきました。
江戸時代にありながら、現代的な出版業の中心的な役割を担った人。
蔦屋重三郎の仕事を追っていくと、温厚篤実な人柄や勘の鋭さなどが見えてきます。幕府を皮肉り、処分を受けてもなんのその。すぐ、次なる一手をうつ商売人としての気骨は頼もしくもあります。
蔦屋重三郎の前半生
宝暦7(1757)年、数えで8才のとき。
蔦屋重三郎は、両親の離婚で親戚の家に預けられました。養父の姓は喜多川。遊郭吉原で茶屋「蔦屋」を営んでいました。
成長すると、吉原の入り口へと続く五十間町にて、貸本屋をスタート。最初は「蔦屋」の軒先を間借りして、生計を立て始めたそうです。
貸本屋として吉原に出入りし、知遇を得ていく蔦屋重三郎。
安永3(1774)年には『細見嗚呼御江戸』をつくりました。
これは「吉原細見」とよばれる、吉原のタウンガイドです。版元は「鶴鱗堂」。100年以上続く老舗。このガイドブックで、蔦屋重三郎は「細見改」とよばれる編集責任者に抜擢されています。
吉原のコミュニティに分け入り、そこで顔の広さやフットワークの軽さを評価されたのでしょう。かわいがられる若者である一方で、なかなかの抜け目のなさも感じられます。
また、安永3年には、蔦屋重三郎オリジナル『一目千本花すまい』を出版。絵本仕立ての遊女評判記。ここでは、北尾重政という大物絵師を起用しています。
さらに安永5年。『青楼美人合姿鏡』を出版。吉原時代の名作として名高い作品です。北尾重政とその最大のライバルの勝川春章の競作というスタイルを起用しています。
ライバルである有名クリエイターを競わせる蔦屋の企画力が光ります。
ついに、安永7(1778)年、29歳のとき。蔦屋重三郎は店先の間借りから自身の店舗に独立し、「耕書堂」を開きました。
安永後期から天明期
この時代の江戸では田沼意次が政治を行っていました。江戸市内は開放的なムードと好景気に沸くことになります。
文化の面からは、これまでの京都&大阪の上方中心であったものが、江戸中心へと移行しつつありました。
100万都市江戸の目覚ましい発展は、「江戸っ子」アイデンティティをはぐくみます。田沼意次時代の放任主義によって、武士も暇を持て余していました。武士とは教養を修めた存在です。彼らの存在も相まって、「蔦屋重三郎」という存在は江戸を盛り上げる起爆点になっていきます。
狂歌
狂歌とは、和歌の詩形にうがち・滑稽・パロディ・ナンセンスなどのエッセンスを加えたもの。
現在でいうところの、伝統的で高度なピアノの技術をもって、アニメ音楽や流行曲などを即席アレンジするYouTube動画のようなもの。「才能の無駄遣い」とはいえ、身近な音楽がより多彩に演奏され、面白いものです。
狂歌も、漢詩や和歌に対する豊富な知識と技法が必要になります。そして、その超絶技法で身近な話題を詠むのが面白いところ
黄表紙
現代でいうところのライトノベルです。大人でも楽しめる軽妙な内容に、浮世絵師による挿絵が飾られ、表紙は黄色。
蔦屋重三郎が仕掛けるムーブメント
蔦屋重三郎は狂歌壇を形成していきます。自身の文芸自体は突出していないものの、有力な作家たちのコミュニティを作り上げました。
いうならば、オンラインサロン「狂歌」の監事をやっているということです。その人脈から、彼の元からは後世では天明期を代表すると評価される作家たちが集まります。
粋で通な文化人が周りに集まる。
蔦屋重三郎の一番の能力はここにあるのではないでしょうか。
彼の元で執筆したのは、大田南畝、朋誠堂喜三二作、山東京伝などのそうそうたるメンバー。
安政9(1780)年には一挙に十点の黄表紙を刊行。一気に、蔦屋耕書堂の名が江戸に広がります。
田沼意次から松平定信の時代に
天明7(1787)年。松平定信が老中首座に就任しました。
松平定信の政治といえば、質素倹約や武芸学問の奨励です。
狂歌や戯作、浮世絵などは不真面目で風紀良俗を乱すものとして目の敵にされてしまいました。
しかし、蔦屋重三郎はそんな政治をあてこすります。
天明8(1788)年、『文武二道万石通』。寛政元(1789)年、『鸚鵡返文武二道』。
どちらも、松平定信を皮肉った作品です。お上に慮るのではなく、自身の商売人としての矜持が優先されています。
さて、今や蔦屋重三郎の「耕書堂」は江戸にも名前を知られた大手出版社。お上も「見せしめ」に動くことになります。
寛政3(1791)年、蔦屋重三郎は財産の半分を没収。山東京伝も手鎖50日という思い処分にあってしまいます。
蔦屋重三郎の晩年期
処分にへこたれてしまう蔦屋重三郎ではありません。彼にとってはどこ吹く風だったのでしょう。次の商機に向けて動き出しているのが、彼の面白いところです。
錦絵
錦絵とは浮世絵の一種です。
まずは、「墨摺絵」と言う黒1色の浮世絵が誕生しました。そこから、刷りの技術の向上に伴って、彩色が増えていきます。最終的に、多版多色刷りの「錦絵」が発明されました。
大首絵
蔦屋重三郎が目を付けたのがこの錦絵です。ここでも、後代に名を遺す浮世絵師をプロデュースするのが彼の慧眼鋭いところ。喜多川歌麿や東洲斎写楽を登用します。
喜多川歌麿による『当時三美人』『江戸三美人』は大ブームに。写楽による役者絵も手がけました。
惜しくも、蔦屋重三郎は寛政9年に亡くなってしまいます。もしも、この錦絵・大首絵に傾注していたら、と思わなくもありません。葛飾北斎との誼もあり、もっと長生きをしていたらあの『富嶽三十六景』も耕書堂からの出版になっていた、かもしれません。
おわり
一度は挫折を味わいつつも、晩年に至っても勢いが衰えない蔦屋重三郎。彼の仕事を通してみてみると、大物の作家たちから愛される人情や、世情に飲まれてしまうだけではないしたたかさなど、大商人にふさわしい人柄が見えてきて、面白いです。
参考文献
増田 晶文 『蔦屋重三郎:江戸の反骨メディア王』新潮社、新潮選書、2024年
鈴木 俊幸 『蔦屋重三郎』平凡社、平凡社新書、2024年
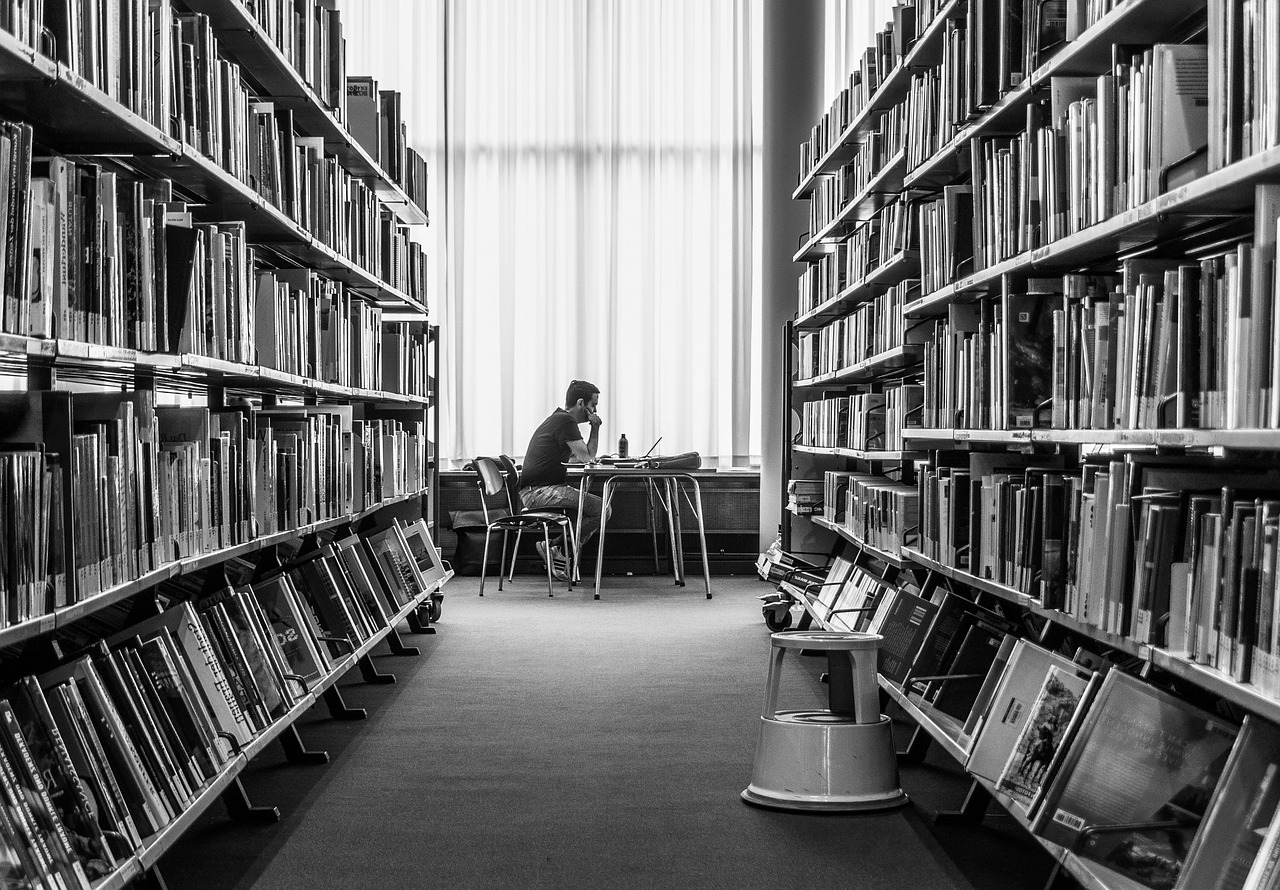

コメント