皆さんこんにちは!
今回は平尾昌宏さんの『人生はゲームなのだろうか? 〈答えのなさそうな問題〉に答える哲学』の感想とまとめです。
哲学、そして身近な「人生」や「ゲーム」という言葉が気になり読んでみました。
本書は、自己啓発書や哲学書とは少し違う、「考えるための」本でした。
- 自分で考えるってどうすればいいの?
- アイディアが豊富に出てくる人にあこがれる
- 説得力のある話ができるようになりたい
こんなふうに思ったことのある人におすすめの本です。
「人生はゲームなのか?」を通して自分で考える本
哲学が何か楽になる方法を与えてくれるなんてことはない。っていうか、そもそも哲学は我々に何かをしてくれるものではないからです。だって、哲学というのは自分でするものだから。何かを得るには、自分で摑む、自分で考えるしかないのです。
p7
哲学というものは、答えをくれるものではなく、考え方を教えてくれるものだということです。
哲学を通じて、自分で問題を掘り下げ、納得できる理由を見つける過程こそが大切。
哲学だけではありません。人生論、自己啓発本、ハウツー本。これらで救われる人はいます。ただ、これらが役立つのは「目的がはっきりしている場合」とき。幸か不幸か目的のはっきりしない人生を生きる我々にとって手当たり次第に読んでも役に立たないと本書では述べられます。
「考えるしかないって言われても、どうやって考えればいいの?」
ここからが本書の重要なテーマです。
心が変われば行動が変わる
行動が変われば習慣が変わる
習慣が変われば人格が変わる
人格が変われば運命が変わる
と、よく書かれていたり、言われていたりします。
自分の内側や環境を変えたいときは、習慣や行動を変えていくしかありません。その大元であり、出発点にあるのが心です。
実際の多くの変化は自分の頭の中から外に向かって起きていくもの。
個人的に、この心とは、感情ではなく、「考える内容」のことだと理解しています。
でも、それができたら、苦労しませんて。
本書は、具体的に「人生はゲームなのか?」という練習問題を通して、考えるとは具体的にどうすることなのかを示してくれます。内容としては、自己啓発的・自己投資的な本ではありません。
徹頭徹尾、「人生とはゲームなのか?」という問題を掘り下げて、あるいは広げていきます。その軌跡を追っていくことで、隠し味として「自分で考える」を感じていくのが本書の醍醐味です。
答えよりも大切なのは前提・理由
答えだけでは実はほとんど意味がないのです。「言える」とか「言えない」という答えが答えとして意味をもつのは、「なぜそう言えるか/言えないか」という理由、前提とセットになってこそなのです。
p27
「人生はゲームではない」と考えて真面目に生きる。「人生はゲームだ」と割り切って楽しんで生きる。でもこれだけでは「本当かどうか分からないふわふわしたものに頼ったり苦しんだりすることになる(p21)」だけです。
答えだけでは足りません。「なぜ」そういえるのか。
納得するために十分な理由・前提を明らかにしていく過程が必要です。
「理解する」なんて言うと、「知らないことを知る」っていう意味だと思っている人がいます。でも、実はね、「分かる」とか「理解する」っていうことのかなりの部分は、「今まで知らなかったことを知る」というより、「なんとなく知っていたけどはっきりしていなかったことをはっきりさせる」ことだったり、あるいは、「自分では気づいていなかったけど、暗黙のうちに前提にしていたことを自覚する」ことだったりするのです。
p30
本書では「人生はリセットできないから、ゲームではない」という答えを例に挙げています。
そして、この答えは怪しいと述べられています。
この意見の「ゲーム」は「コンピュータゲーム」のことで「プロ野球の試合」のことではないでしょ? プロ野球の試合はゲームと言えそうですが、「まった、今のなし!」とは言えません。「ゲーム」とは何か?
これで、「考える」ことが少しわかってきました。
隠れた前提や理由や定義を明らかにしていく。
どうやって考えればいいのかわからない状態から、少しだけ進むことができました。
「考えること」に終わりはない。疑問、補足、拡大していく。
本書はさらに踏み込んでいきます。
「はっきりわかった」ことを足場にして、一歩でも半歩でも「人生はゲームなのか?」の議論を進めていきます。答えを出すだけでなく、そこから生じる疑問や「この場合は同じように考えられる?」という質問に答えることで、答えはより掘り下げられていく。
そして最後には「人生はゲームではない」という結論と、いくつかの「じゃあどうするのか」が示されます。
ただし、大切なのは結論ではありません。ここまで読んでみれば、本当に大切なことが分ると思います。
たぶんですけど、「もっと深く、もっと突っ込んで」という面を見ると、「やっぱり哲学って答えがないんだな」と思ってしまう人もいるだろうと思います。だけど、そうじゃなくて、例えば「人生はゲームか」については一定の答えが出せたわけです。ただ、たとえ答えが出せたとしても、その上で、「もっと先まで、もっと広く」、あるいは、「もっと深く、もっと突っ込んで」っていうのも可能だってことです。それは「答えがない」というのとはまったく違ってて、言うんだったら、「哲学には終わりがない」と言った方がいい。区切り区切りで、一定の答えを出すことはできる。だけど、それをさらに広げたり掘り下げることもできる。そういう意味では、終わりがない、いつまでも続けられる(楽しい!)。
p180
一番感銘を受けるのは、その過程を楽しむということ。方法を考える以前に、とても大切な姿勢を教えられました。
細部を考える、補足し、修正していく。
すると、全体像も変化していく。
「考える」ことを通して、具体と抽象を行ったり来たりする感じ。
「人生はゲームなのか?」という一見、シンプルな問題から随分と遠くまで議論が及びました。このダイナミクスがとても面白い一冊です。
さいごに
自分で考えることが大切だ!
↓
………。(フリーズ状態)
↓
分からん!
こんな不甲斐ない状態であった僕ですが、少しだけ考えることに対する解像度が上がりました。
「自分で考えることが大切だ!」と意気込んだものの、やっぱり最初は思うように進まない…。そう、最初はフリーズ状態に陥ることもあります。でも、それこそがスタート地点。何もわからないところから一歩一歩進むことで考える力も磨かれていきます
少なくとも最初の一歩で何をしていくのか分かりました。
本書では、もっと具体的に、そして哲学史上の議論も参照しつつ、なおかつ、とても読みやすい文体で、書かれています。とても読みやすく、得るものも大きかった本でした。
気になった方は是非ともお手に取ってみてください!
それでは、最後までお読みいただきありがとうございました!
書誌情報
平尾昌宏『人生はゲームなのだろうか? 〈答えのなさそうな問題〉に答える哲学』筑摩書房、ちくまプリマ―新書、2022年、キンドル版

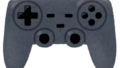

コメント